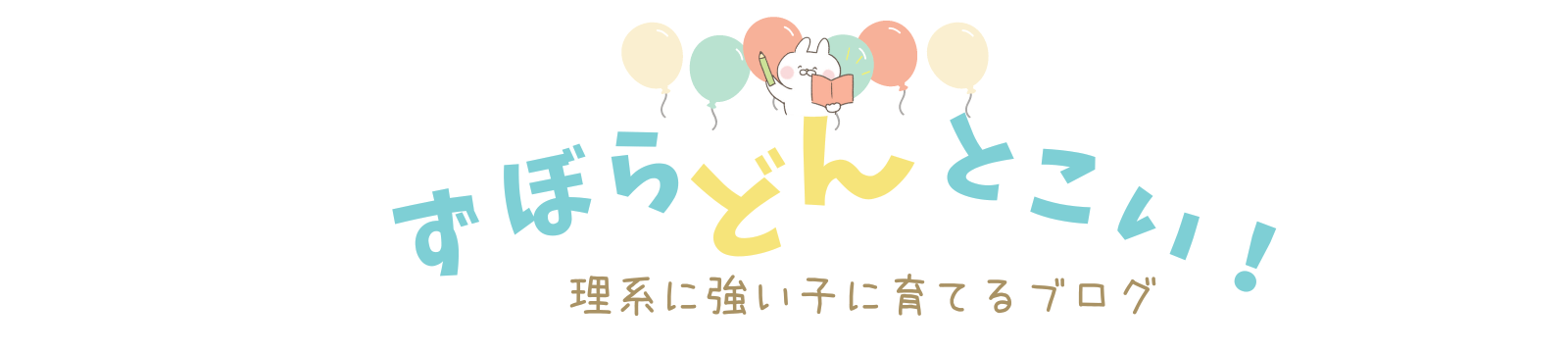「ずぼらどんとこい!」へお越しいただきありがとうございます!
ここでは、このサイト(ブログ)ができた経緯についてお話させていただきます。
文系主婦が「理系分野に強い子に育てたい!」と
思った理由

もともと私は数字が大の苦手で、文系コンプレックスがあります。
「こんな時、計算が早かったら」「どちらの方が安いかパッとわからない」「現象を説明・理解できない」
「お金の話が難しい」「数字ができたら仕事も早くなるのに」「理系なら就職も有利なのに」…
いろいろありますが、「理系分野が得意だったらどんなに良かったか!」と思うことがたくさんありました。
もちろん夫を始め、理系の友人が多くいるので、理系だから苦労しないわけではないことも承知しています。
それでも子どもたちには、私と違って理系分野に強い子になってほしい。それには3つの理由があります。
論理的思考を始めとした様々な能力が身につく

自然現象に対して「なぜ?」と疑問を持って調べる。
プログラミングのエラーをもとに、「どうしてこうなったのか?」と考え試行錯誤する。
このように、理系科目は「何が原因で、なぜこうなったのか?どのようにすれば解決するか?」と考える思考=論理的思考能力を上げるのに最適な科目です。
こうした思考は将来どんな職業についたとしても重要な思考であり、生きていくために重要な思考です。

小さいうちからこの論理的思考を身に着けておくことが大変重要であると考えています。
他にも問題解決力、粘り強さ、理解力、物事を整理する力など、今後生きていくために頼もしい能力を同時に身につけることができます。
将来的に有利である

そもそも「文系」「理系」という分類は日本独自のものであり、線引きも曖昧です。
そのためここでの「理系」は大学の学部分類でのイメージにはなりますが、理系に進むほうがその後の就職においても有利なことが多いです。

理系は平均給与でも文系と100万程の差がつくと言われています!
さらに今後はAIをはじめとする技術革新が急速に進むことが予測されます。
日本でも他の先進国に倣い、国をあげて「STE(A)M教育」や小学生からの「プログラミング学習の義務化」を推進している点を考えると、今後の理系需要はますます高まってくると考えられます。
今後はAIやデータを活用する仕事か、対人コミュニケーションを必要とする仕事、芸術系の仕事が残ると言われています。
そのため、将来の選択肢を多くするためにも、理系分野は苦手にしないほうが良いと考えています。
選択肢を広げることができる

理系出身者が途中から文系に転身することは珍しくありませんが文系出身者が途中から理系に行くことは困難です。
なぜなら理系分野そのもの(特に数学)が、小学校〜大学までの知識・思考の積み重ねの上に成り立つ性質のものだからです。
また文系の学部であっても、例えば法学は論理的な思考が必要になりますし、経済学や心理学、社会学などでも数学の知識や理解が必要になります。
理系の人が文系へ転身できるのは、文系にも応用できる論理的な思考力や数字を理解する力を既に身につけているから。

実際、理系専門職の夫は、現代文は常に満点だったそうです!
将来的に子どもが文理どちらを選択するにせよ、小さい頃に理系分野に対しどのように関わったかは大変重要であると思います。
文系親が理系の子に育てるには

でも文系なのに、理系脳の子に育てられるの?
こうした疑問がおありかと思います。
そこで私は文献を読み漁り、データサイエンティスト(AIを駆使する職業)の夫や、理系の友人たちに幼少期のころどんなことをしていたのか聞いてみました。
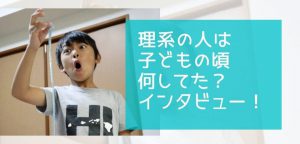
その結果、
- 子どもの頃の自然体験を多くしていた。
- 家庭独自の算数ドリルなど、楽しく勉強できるように工夫されていた。
- 学校で習ったことを、アウトプットする機会があった。
というような、思ったよりもシンプルであることがわかりました。(※文系との比較を定量的にしたわけではないので、今後載せていきたいと思います。)
重要なのは「アウトプットの機会」
個人的に重要と思うのは、アウトプットの機会です。
いま、小学一年生の息子は将来的にプログラミングを学ぶことを踏まえて、ロボット教室に通っています。
レゴが好きだったこと、プログラミングの前段階という意味もありますが、きっかけはこちらのツイート。
積み木の積み上げでも成長を感じる✨
左:2歳息子
右:3歳息子 pic.twitter.com/uRIYvovKUs— れんし@積み木っ子の父 (@Rennshi2) April 26, 2022
3歳でこのクオリティに衝撃を受けました。
ご家庭では、もともと積み木遊びをしていただけでなく、 子どもの「夢中」を広げるために積み木教室にも通っているようです。

こうした子どもの好きなことや、広げていくことは親の役目として大変重要だと思ったんですね。
また脳には発達の順番があり、タイミングを逃すとあとからは身につかないと言われる能力もあります。
空間認識能力などがまさにそれにあたります。
一方東大生のほとんどは、子どものことに「熱中体験があった」とも回答しています。
つまり幼少期から思春期までの脳の発達が著しい子ども時代に、どれだけ「子どもの夢中」を高め、アウトプットできるかが能力を高めるのに重要だと考えられます。
「夢中」を広げるブログにしたい

以上から、理系分野を通して、子どもの「夢中」「熱中」を広げることができる方法をご紹介するサイトを目指しています。
ロボット教室やプログラミング教室、科学実験などをはじめとしたおすすめの通信教材について、実際の体験・口コミを踏まえてご紹介しています。
教室の特徴、通うと伸びる能力を比較することで、公式HPではわからないポイントや、他サイトにはない視点から比較することを意識して更新しています。
もし「レゴが好き」「細かい作業が好き」「ゲームが好き」「生き物が好き」「実験や観察が好き」など、
ちょっとした伸ばしたいきっかけを見つけたら、ぜひこのサイトを参考にしていただければ幸いです。
ちなみに、子ども達は
- ロボット大好き、計算が得意な小1息子と、
- 2歳でひらがなをマスター、足し算引き算ができる絶対音感アリ年少息子
に育っています。

文系親でも無理なく楽しくできる方法をお伝えしていきます!