この記事では
- 子持ち主婦でも、公務員として働きたい!
- 30代パート主婦だけど正社員として働きたい!
- 子持ちなので正社員として雇ってくれるか不安
という方へ、30代子持ち主婦でも公務員試験に合格した方法についてお伝えしています。
正社員として働くには、「子持ち主婦への理解がある職場」を見つけるのが必須ですが、実際見つけるのは難しいですよね。
一方中途での採用も多く、子育てへの理解があり、休みも取りやすいのが公務員。
家事育児に忙しいのに時間がとれない…
子どもがいると合格に不利なのでは?
とも思いますよね。
実は、子持ち主婦が公務員に合格するには知っておくべきコツがあるんです。
この記事では、
- 正社員歴が短い(2年半)
- パートを転々
- 30代
- 幼児2人持ち主婦
である私が、倍率20倍の公務員試験(市役所事務職)に合格したコツ
についてご紹介します。
合格すれば、公務員として子育てに配慮ある職場で、長く勤めることが可能です。
実際、合格するまでの勉強時間はそれほど無くても大丈夫。
すでに正社員で、公務員への転職を考えている方も参考になる内容になっています。

「これなら自分にもできるかも!」と思えると思います。ご自身の自己実現のために是非参考にしてください。
詳しい履歴書の書き方や面接については、実際に書いた文章をもとにnoteにて500円で販売中です。
ある場所で面接練習ができる裏ワザ、志望動機・自己PRに何を書いたか、実際に面接で聞かれたことなどを知ることができます。
子持ち主婦が公務員を志したきっかけ

本題に入る前に、少しだけきっかけについてお話します。
子どもが成長したあとの不安が大きくなった
私は大学卒業後、金融機関で2年半正社員で仕事をしたあと結婚。
夫はだいたい2年ごとに転勤があったため、その度に業種バラバラで、パートをしていました。
その間子どもを2人出産しているので、専業主婦期間もあります。
正社員経験が短いため、もう少し働きたい欲はありましたが、
- 子どもともっと一緒にいたい
- 夫が仕事で忙しい
- 両家の両親は遠方で頼れない
などの理由から、家事育児は自分しかできないと諦めていました。
しかしある日ふと、「子どもは大きくなったら親から離れてしまうのに。その後の自分には何が残るのだろうか?」と思うように。
お金や年金も心配だし、社会のなかでの生きがいや達成感がもう少しほしい。
やっぱり正社員として働きたーい!という欲がぐんぐん湧き上がってきました。
えっ!子持ちでも公務員になれたの!?目指したきっかけ

大学時代の友人と久しぶりに連絡をとった時のこと。

私、いま市の職員になってるよ〜。
との言葉を聞きました。
彼女もまだ2歳の子どもがいて、実家も遠方。
育休後正社員として勤めていたけれども、
両立が難しくなり市の公務員職員採用を受験したとのこと。
今の職場では子持ちに対する周りの理解もあり、入ってすぐ時短にしてもらうこともできたようで、羨ましく思いました。
しかも「1日1時間ぐらいしか勉強できなかったし、数ヶ月しかやってないよ」
とのこと。え、それでも受かるんだと…

1日1時間の勉強なら、私にもなんとかできるのではないか!?と思い、公務員を目指すことにしました!
子持ち主婦でも難しくない!公務員に合格するコツ

いよいよ子持ちパート主婦でも、公務員に合格したコツをご紹介します。
ちなみにここでは、専門知識や資格が不要な、公務員「事務職(一般)」の受験を想定しています。
受験する自治体を選ぶ際のポイント
- 競争が比較的低い自治体を選ぶ
- 自治体が筆記・面接どちらを重視するかチェックする
- 年齢制限はクリアできるかチェックする
(※制限があっても年度によって変わるので注意です。)
競争率が比較的低い自治体を選ぶ

子持ち主婦・パート主婦は勉強時間の確保が難しいです。
正社員からの転職なら違ってきますが、専業主婦やパートだった場合は
やはり他の受験生と比較すると不利になります。
そのため、正直県職員や政令指定都市などの大きな自治体の合格は難しいことがあります。(筆記に自信があるなら別ですよ!)
地方都市の職員など、スケールを小さくしてみましょう。
そのぐらいの単位であれば、転勤も遠くへは行きません。
また地元だけでなく、行ける範囲の他の自治体はどうか?も検討してみましょう。
地元でなくても合格した話というはたくさん聞いているので、他の自治体だからといって受験は不利になりません。

というかいざ入ってみると、地元でない自治体のほうが知り合いに会いづらいですし、クレーマーに顔も覚えられなくていいなと思いますよ(笑)
あまりに遠いと、今度は移動だけで時間がなくなります。
もし合格したらどのように通勤できるか?保育園は近くにあるか?もチェックです。
自治体が筆記・面接どちらを重視するかチェックする
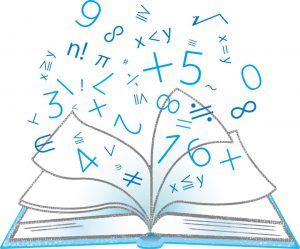
ここはあなたが確保できる勉強時間や、自治体の試験方針によって変わります。
- 1年以上先の合格を目指していて、勉強し続けられる
- 勉強が比較的得意
または
- 面接に全く自信がない
のであれば、筆記試験重視の自治体でOKです。
逆に
- 試験日が近い
- 勉強時間がとれそうにない
- 面接のほうが自信がある
または
- 経歴も面接もそれほど自信はないが、今現在パートやアルバイトをしている
- 面接はそれほど自信がないが、
- 正社員歴が長いor受験する自治体と親和性のある職場で働いていた
のであれば、面接重視の自治体がいいと思います。

面接に自信がなくても、面接重視受けていいの?
と思うかもしれませんが、
中途社会人枠(新卒や第2新卒ではない)であれば、正直面接重視のほうが
筆記より有利に働くと思います。

なぜなら、職務経験があるから!
あなたの「見せ方」によって
面接のほうがずっと合格する率を上げることができます。

「受験する自治体との親和性」に関しては、
例えば福祉系の学部を出ていたり働いていた場合は、面接で福祉系の課での活躍をアピールすることができます。
やりたいことがあったり、自治体の重視する事業と自分のしてきたことが合致するようであれば必ず面接でアピールしましょう!
年齢制限があっても年度によって変わる
公務員になるには年齢制限があります。

30代じゃまだ若いじゃん!
と思う人もいるかもしれませんが、残念ながら公務員だともうアウトなことが多いです。
35歳でギリギリあるかないか。場所によっては受験することができません。
ですが近年では公務員試験でも中途採用枠を設けているところもあり、自治体によっては40歳以降も募集しているところがあります。
定年手前まで採用枠を設けている所も。
自治体によって異なるので要チェックですが、年度によっても違ってきます。
/
今年は中途採用枠やってなくても、去年はやってた!
年齢制限の上限が今年から上がった!
\
というところもあります。
そのため
今年度なかったとしても職員の欠員状況によって、来年度に年齢上限が上がる可能性もあるので、諦めてはいけません。

ちなみに中途採用枠だと、アルバイト経験や勤続年数が関係してくることもあるので、応募条件についても要チェックです!
また「受験ジャーナル」で過去の公務員試験の出題内容や、過去の年齢の枠などを調べることができます。
自治体のHPに載っていることもありますよ。
受験する自治体を決めた後の公務員試験対策!

私は中途採用枠を実施している、近隣の市職員を受験しました。
中途の場合は即戦力が期待されるため、受験生には今まで正社員として仕事をされていた人がたくさんいると思われます。
「子持ち(パート)主婦」という不利な中で戦うには、
- まず筆記試験を万全にする
- 履歴書を良く見せるように工夫する
- 情報を入れる
ことが特に重要です。
筆記試験について
正直政令指定都市でない市役所などの受験で、かつ中途採用枠だったりするとあまり勉強の方は重視されていないような気がします。
みんな同じように、時間が無い中で勉強していることがわかっているからです。
また公務員自体、近年は知識偏重より人間性ということで、面接を重視する傾向にあります。
社会人の場合は即戦力を期待しているので、
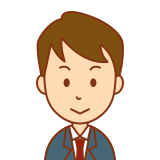
筆記がだめでも、職務内容については面接で聞いてみたい
という採用側の本音もあると思います。

これは自治体規模や何を重視するかでもちろん違いますが、
社会人の場合は筆記は合格最低点ぎりでもOKか、
ちょっと大目にみられている可能性があります。
その代わり、面接は厳しく見られるかと。

そうでないと、どう頑張っても、新卒には勝てませんよね…
よく公務員試験には「このぐらいの勉強時間が必要です」と書いているところもありますが
正直、どのくらい必要といえるかはその人の状況、自治体の規模感、職種枠で受けるかによって全く異なるので、一概にはいえません。
勉強期間が長ければ長いほどいいですが、「短いから絶対受からない」とは言い切れないのですよ!
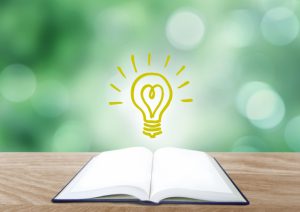
ただそうはいっても、私はさきほどの2人より年齢・経歴の面で不利な状況だったので、

筆記は確実に押さえておきたい!
なるべく効率的に得点がとれるよう対策しました。
時間的には、1日平均1時間、1年間。
できない日もあったので概ね300時間ぐらいです。
どの公務員試験においても、一番重要視され、得点のキモとなるのが、
数的処理・判断推理という数学や図形、推理力や論理的な能力が問われるの科目。
とにかく数字が苦手だった私はそればかりやっいました。

というか、筆記に関しては95%それしかやってません。他は捨て!
ちなみに数的処理・判断推理で参考になる本といえば、畑中敦子氏 の著書一択!です。
検索してもこの人しかほぼ出てこないんじゃないかな?ってぐらい超有名人。
数字が苦手な私でも解説がわかりやすく、独学でほぼ理解できました。
改訂の度に微妙にデザインが変わっているので、通常購入しようとすると迷うと思います。こちらが最新版になります。
表紙がワニデザインであることから通称「ワニ本」と呼ばれていますが、年によってはカンガルーの絵になったりします!(笑)
「過去問500」も他の科目確認のために、最後の方にやりました。
これも公務員試験受験者の中では有名な本です。
子持ち主婦が公務員合格するには、
とにかく「履歴書」づくりに注力する

一番大事なのは「履歴書を高いクオリティで仕上げること」!
これに尽きます。

面接が大事って言ってたから、面接練習じゃないの?
と思うかもしれませんが、面接は、履歴書を基に進めていきます。
もちろん面接では履歴書にないことも質問されるので、質問を想定して準備しておくこと(面接対策)も、この履歴書づくりの作業工程に含んでいます。
つまり面接練習よりも、前段階の準備に時間をかける必要があると思っています。

私も添削やリライト、調査を含めて最低2週間はかかったと思います。本当は1ヶ月くらいかけたほうがいいと思います。
考えるべきエピソード・ポイントなど具体的な履歴書の書き方については、
実際に書いた文章をもとにnoteにて500円で販売中です。
ある場所で面接練習ができる裏ワザ、志望動機・自己PRに何を書いたか、実際に面接で聞かれたことなどを知ることができます。
子持ち主婦から公務員は本当に難しいのか?まとめ

- 子持ち主婦であっても、30代以降であっても公務員に受かることは可能!
- 競争率が高すぎず、自分に合った試験内容の自治体を探してみる。
- 筆記試験は、社会人に対してはそこまで重要視されていない可能性がある。
- 1日1時間の勉強ができれば、数ヶ月で受かることも。捨て科目を作って効率的に勉強しよう。
- とにかく「履歴書づくり」=「面接の準備」が一番大切!
向こうは新卒と違って即戦力を期待しているため、
筆記試験より、ここが一番知りたいところ。
何かしら公務員の仕事に活かせるあなたのエピソードは必ずあります。
頑張ってひねり出して、仕事に応用できることをアピールしましょう。
要は「場所を選ぶ」ことと、「見せ方」を意識することができれば、子持ち主婦であることは関係ありません。
子どもがいることについて聞かれることはありますが、堂々と答えられてさえいれば大丈夫。
要はどんな質問がきても対応できるように準備しておくことが一番重要です。
そして、「合格した後の姿」をしっかり想像しておくことも、あなた自身のために重重要。

先程登場した子持ち主婦の友人は
入ってすぐ時短がとれましたが、
私の合格した自治体では時短はできればやめてほしいと言われ…
それを事前に知っていれば良かったのにと思うこともありました。
時短ありきで考えるのは良くないですが、事前に情報源があれば積極的に活用しておきましょう。
(匿名で事前に、人事課に質問しておくのもアリだったかも…と今では思います)
「副業にあたるのでは?公務員って禁止じゃないの?」と思う方もいるかもしれませんが、その他にも人事の対応に思うところがあり、合格は事実ですがその後断っています。「もったいない!」と今でもよく言われますが…
ただ友人いわく、
「両立は時短であってもやはり大変」だそうですが、子育てに理解があるので
なんとかやっていくことができているそうです。
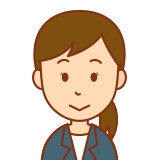
本当は時短だと時間内に仕事が終わらないので、めっちゃ仕事早くなった
というメリットがあったとも言っていました。
仕事を頑張るお母さんの姿を見せることは、子どもにも良い影響があります。
「子持ちじゃ公務員なんて受からないかも…」と諦めず、
是非、今から情報収集からしてみてください。
受かるチャンスは必ずありますから♪

※今回の公務員試験に関して、もっと知りたい!など質問ございましたら、一番下のコメント欄か、お問い合わせよりお願い致します。

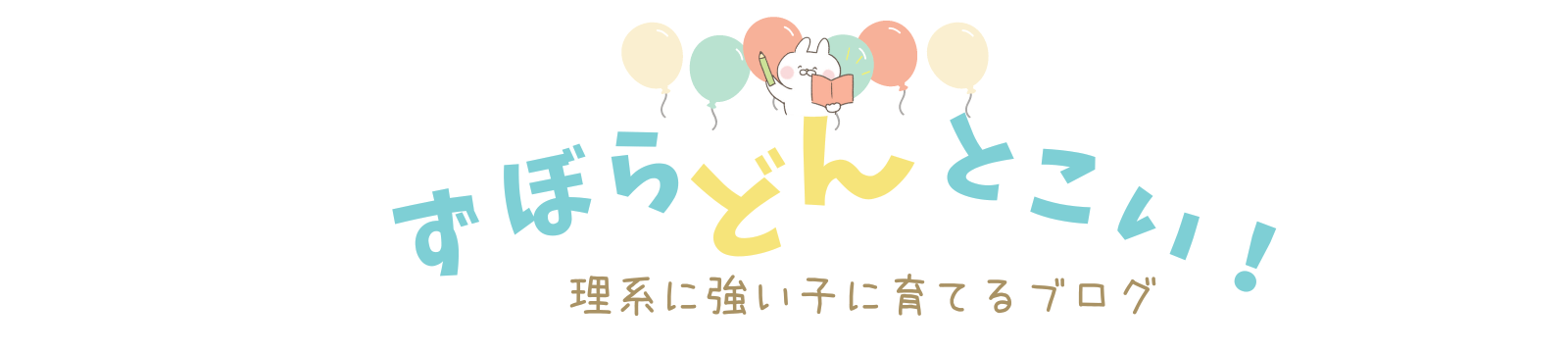

コメント